~ベースアップ評価料の運用から1年を振り返って~
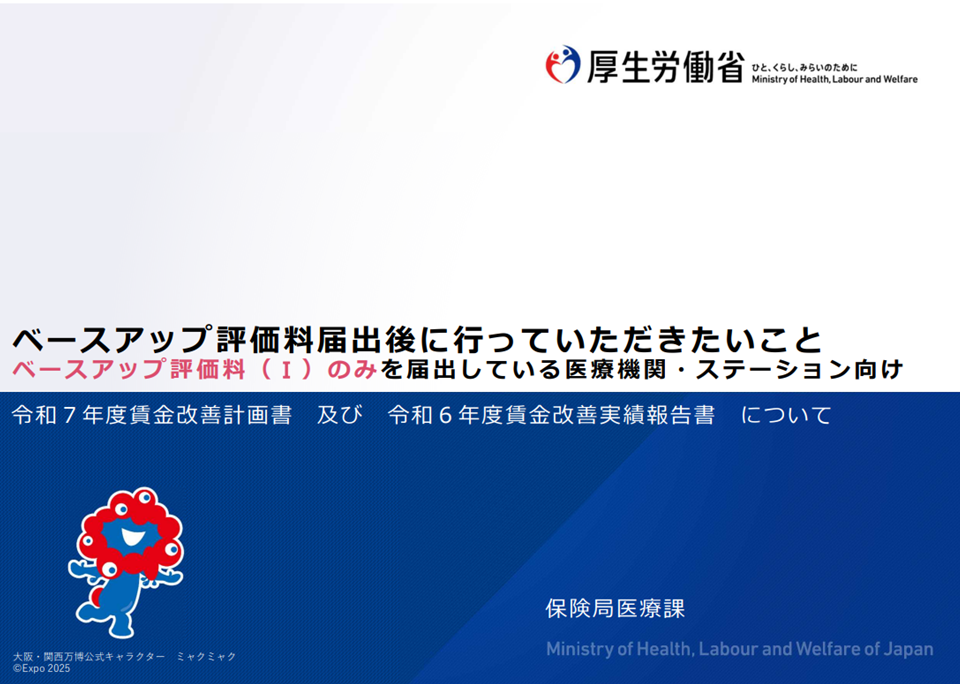
ベースアップ評価料の制度が開始されてから、早くも1年が経過しました。制度開始当初は、制度の複雑さや手続きの煩雑さから、導入に対する慎重なご意見や不安の声も多く寄せられておりました。しかしながら、実際に運用を進めていく中で、手続きの流れも見えてきており、現在では実施する医療機関も増えてきました。 弊社で制度導入をサポートさせていただいたクリニックでは、月額5,000円~8,000円程度のベースアップが実現しており、制度としての実効性を感じているところです(※金額は初診・再診の件数により変動するため、あくまで目安です)。 導入クリニックからは「やってよかった」というお声を頂くことも多く、現時点ではマイナスの意見は特に寄せられておりません。人材確保がますます難しくなる中で、ベースアップという形で直接職員の処遇改善に繋がる本制度の意義は、極めて大きいと実感しています。
手続き面の進捗と今後
今年(2025年)の3月までに評価料の算定を開始した医療機関では、6月末(※投稿日時点では既に期限超過しています)までに「賃金改善計画書」の提出が求められ、さらに8月末には「実績報告書」の提出が控えております。弊社でもこの6月は他の業務と重なり非常に多忙ではありましたが、受託中のクリニック様については無事、期限内に提出を完了いたしました。 提出にあたり、前年度の収入実績や賃金改善額の集計は6月末までに提出した計画書の段階で済ませているため、実績報告書の作成は比較的スムーズに進む見込みです。 また、制度が簡素化されたことで、届出負担は以前より軽減されており、「ベースアップ評価料の見込収入 < 賃金改善額(法定福利費込み)」という考え方の定着により、適切なベースアップ額の算出も行いやすくなりました。
運用上の工夫とご提案
例えば、ひと月あたりの評価料見込収入が30,000円で対象職員が5名いる場合、1人あたり5,500円のベースアップで、5名合計で27,500円。これに法定福利費(16.5%)を加味すれば32,037円となり、見込収入を上回ります。このような実務的な運用指針も整理されてきました。 実際、弊社でご支援したクリニックでは、前年度と今年度で大きな変更なく継続実施が可能となっており、今後もこの「丁度よい塩梅」での運用が主流となっていくのではないかと考えています。
導入の意義と外部支援の必要性
導入にあたっては「費用対効果」や「制度の複雑さ」がネックになりがちですが、ある先生のお言葉が非常に印象的でした。 「物価高騰、人手不足の中で、従業員の賃上げができる制度があるなら、少々費用がかかってもやらない理由がない」 まさにこの言葉に背中を押され、弊社でも本制度への本格対応を決断いたしました。 また、受付業務を担う方にヒアリングしたところ、「制度の届出で業務が煩雑になったということはなく、むしろ届出等の大変な部分を社労士に任せて良かった」といった前向きな声を頂きました。今後もこうした外部支援の意義は高まると感じております。なお、まだベースアップ評価料の届出を実施していないクリニックも一定数あるのが現状ですが、ヒアリングを実施した受付業務の方からは「なんでやらないんでしょうか」と逆に不思議がられるようなご意見もありました。それだけ、実施してみて得られた効果やメリットを実感されているということだと思います。
弊社のサポート費用について
1年間の制度運用を通じて、申請の流れや必要工数も把握できてきました。これに伴い、弊社では以下の費用にて申請代行を承っております。 対象職員人数 費用(1年度あたり)
【1人~4人】 20,000円
【5人~9人】 25,000円
【10人~19人】 30,000円
【20人以上】 30,000円+((対象職員人数-19)× 500円)
※1年度につき上記の金額となり、実績報告のみの場合でも上記同様の金額となります。また、実績報告のみのご依頼は原則、受付けておりません。顧問先様のみのご対応となります。
